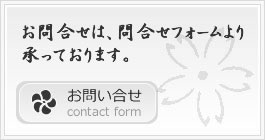Archive for the ‘弓の心得’ Category
麻弦を上手に使用する方法
Q7.麻弦をなるべく長持ちさせるには、何に注意すればいいでしょう?
日本弓には麻弦が最も適しています。麻弦の冴えたさわやかな弦子は、先手から全身に伝わり、化繊の弦では到底味わえないものがあります。
最近は麻弦を知らない方が多くなりましたが、日本古来の武道としては淋しい現実であります。せめて主要な大会や昇段審査では麻弦の弦子を響かせていただきたいと願っております。
晴れの舞台に於ける弦切れの配慮は理解できます。しかし弦切れの「失」の適切な処置は特に見応えがあり、日頃の弛まぬ修練を経てのみ身につく、奥行きのある質の高い体配を表現する絶好の機会となり、当然「失」を補うに十分な評価を得られるものと思う次第です。
優秀な麻弦は上手に正しく使えば300射前後はもちます。合成弦使用での弓の消耗度の大きさと比較しますと、経済的にはあまり差はないように思います。弓道を高い意識で追及される方は、是非とも麻弦をお使いいただき、奥行きのある弓道を目指していただきたいものです。
さて、麻弦をなるべく早切れしないように長持ちさせる方法ですが、麻弦の切れる箇所はおおむね上下の弦輪の結び目と中関です。この3箇所には特に配慮が必要です。よく耳にするのが、弦輪の結び目からの抜けるような切れ方です。これは弦輪部分の仕掛けを太くすれば防げるのですが、弦子が悪くならないようなるべく細く作ってあります。
弦輪の位置を左右に動かぬよう、小さめに作る方が多いですが、これは抜け切れの大きな要因にもなります。弦輪の結び方は、結び目が弓ハズの肩より内側になる程度に、上下とも大きめに、そして強く締めるようにして結んで下さい。また弓力に対して矢の重量は重いほうが切れにくくなりますので、適切な組み合わせを心がけて下さい。
冬場になると、弓力は強くなり、逆にクスネは低温のため硬くなり、乾燥して繋ぎの力は弱まります。この場合、マグスネをかけて摩擦熱でクスネの繋ぎをよくしなければなりません。ただし弦輪の結び目にはマグスネが使えませんので、こういう場合は温めたり、指先でほんの少し水をつけて湿らすといいでしょう。弦が切れやすい冬場は、行射に入る前だけでなく途中でもマグスネは掛けた方が良く、夏場より矢をやや重く(2?3分:1グラム前後)することは必要です。摩耗した矢の根を新しくするだけでも効果はあります。
皆様の研鑚、配慮を願っております。
最適な弓の長さ
Q8.弓の長さを選ぶ際、何を基準に決めればいいでしょう?
以前は身長160センチまでは並寸、170センチ前後は二寸伸、特に背の高い方は四寸伸弓を使用するのが通常でしたが、今は身長160センチでも90センチ以上の矢束を取る方も珍しくなく、身長と矢束の関連が以前とは異なってきています。御自分の最長の矢束を確認しておくことは不可欠であります。
ファイバー弓から弓道を始めた方は、先手を強く握り、捻り込む手の内になりがちで、笄を起こす大きな要因となります。強い先手の働きは鋭い矢飛び、弦子、的中を求めるには重要で、大事な射枝の一つであります。弓に負担の少ない、先手の剛弱を生かした柔らかい中押しの手の内の会得を目指すべきでありますが、これは日々の習練のなかで身につくものです。
かつてファイバー弓に馴染んだ方、笄を出した経験のある方、合成弦使用の方、先手の堅い方、左利きの方、20キロ以上の強い弓使用の方など一つでも該当したら、笄を出す可能性はあります。御自分の射枝の傾向、特性を考慮に入れ、柔軟に対応し、矢束に対して余裕のある長めの弓の使用が賢明であります。
長い弓は矢飛びが悪いように思われがちですが、並寸85センチ、二寸伸90センチ、四寸伸95センチで弓力計測するため、同じ弓力表示の場合、並寸が実際は強いことから生じる勘違いです。例えば二寸伸の15キロ表示は、並寸の矢束では14キロ弱に相当します。
日本弓の射法上、胸弦が長い弓ほど右奥にくるため「会」での安定感とたっぷり感があり的中の向上が望めます。
近年、特に若い人は矢束を長くとりますので、四寸伸の使用者も増え、女性の二寸伸使用の方も増えてきました。このことは理にかなった当然のことであると思います。
上記の並寸、二寸伸、四寸伸の各計測値が、取りうる矢束の限度と考えて良いと思いますが、ご自分の射の傾向を極力考慮して長さを決めることが肝要です。
合成弦との上手な付き合い方
Q6.弓の故障を起こさずに、合成弦を使用する方法を教えてください。
合成弦の一番の長所は切れないことであります。この長所は一方で、弓に負担をかけ、故障・破損を招く原因にもなります。合成弦の特性を理解し、弓に負担をかけないための対策や工夫をこらしてお使いになることが大切です。
合成弦には離れの衝撃を吸収する能力はありませんので、麻弦使用の場合よりも重めの矢を使い、絶対に筈こぼれをしない細工をすることが何よりも大切な事です。以下、具体的な留意点・対策を記します。
中関・矢筈に加工する
 【写真17】
【写真17】
筈こぼれの状態(空筈)で離れると、必ず弓の反転を起こします。合成弦を使う際には、空筈を起こさないための対策が必要です。具体的には、中関をきつめに作り、矢筈にも丸ヤスリで奥に膨らみを持たせるような細工をします(写真17)。また空筈の一つの原因となる筈割れを防ぐため、中関を作る際はクスネやアラビックヤマト等の固まってもソフトな接着剤を使います。
同じ弦を切れるまで使用しない
弦輪の部分を巻き足して太くしてあるのは、衝撃をなるべく軽く受け止めるためです(この部分が太すぎると弦子がしないため、巻きは必要最小限にしてあります)。矢数が増えるに従って輪の部分は段々細く、堅くなりクッションの役目をしなくなり、やがて関板の弓ハズ肩の外竹側に縦割れが起き、使い続けると、弦輪が芯、関板に食い込み修理不可能な状態になります。この破損は強い弓ほど顕著です。
もし縦割れが見つかったら、なるべく早い時点で瞬間接着剤を注入し、縦割れの進行を防ぎます。日頃の点検を怠らないようにして下さい。麻弦ならば200~300射引ければ十分納得できる矢数であることや、合成弦の使用で弓が受けるダメージ、麻弦との価格差等を考え、同じ弦を切れるまで使用せず、合成弦であっても200?300射を目途に替えるほうが得策です。
重めの矢、箆張りの強い矢を使う
矢の重量と弓の寿命、弦子、弦の持ち具合には大きな関連があります。矢飛びが悪くならない範囲でなるべく重い矢を使うべきです。
矢の重量を好みで選ぶのは間違いで、弓力に応じた重量と、箆張りの強い適度な太さの箆で作られた矢を選んで下さい。重目で箆張りの強い矢ほど弦の持ちが良く、離れの衝撃を和らげ、先手の感触をソフトにし、笄も起こりにくく良い弦子も出ます。
弓力に対して軽い矢は弓体を強く叩き過ぎるため、左右のブレが大きくなり弦子は出にくいのです。弓力に対してやや重いほうが弦子は出ます。
竹矢の場合、細目より太目の方が通常箆張りが強いものです。細めの箆は重量に比して箆張りが弱い場合が多く、箆張りが弱いと離れの衝撃を押さえる働きも弱くなり矢所も散る傾向があります。
合成弦の長所と短所
Q5.合成弦を使っていますが、麻弦と比べて何が違うのでしょう?
弦と言えば、以前は麻を素材とした麻弦のことを指していました。しかし今日では、化繊素材の合成弦が主流となっています。弦というのは切れるのが当たり前だったわけですが、合成弦が登場したことで「弦は切れないもの」との危険な感覚さえ芽生え始めており、その強靭すぎる特性ゆえに弓に大きな負担をかけ、故障を招いているのが事実です。
麻弦を知らない弓士も多いのは残念なことでありますが、麻弦には和弓と共に歩いてきた長い歴史があり、弓の弦としての適性は言うまでもないほど優れております。麻弦は、耳に心地良い冴えた弦子を響かせ、弓の性能を極限まで発揮させます。加えて弓の負担を和らげる独特の特性で、笄(こうがい)や首折れ等の故障を極力抑えてくれます。
一方、合成弦は「丈夫さ」を第一義に開発されたものであり、弓がそれによって受ける大きな負荷を考慮して作られてはいません。だからといって、合成弦そのものを否定するのではなく、必要不可欠な用具ゆえに長所を活用し、欠点を補う工夫をしたうえで使用していただくことが重要かと思います。麻弦と合成弦の特性の違いを認識しないで、麻弦と同じ感覚で合成弦を使用していれば、ある日突然弓の破損や支障を招くことは必至であります。
弓が最も負担を受けるのは、会→離れ→弓返りの過程であり、特に離れから矢を送り出しつつ弓返りに至る時の、瞬間的な衝撃は非常に大きなものであります。この衝撃を和らげるのが、矢の重量と箆張り(のばり:矢のしなり)の強さであり、射枝面の先手の中押しの柔らかい手の内、左右均等の離れであります。そして、かつては全ての人が使用されていた麻弦が、弓の負担を軽減する大変大きな役目を果たしていたことを知っていただきたいのです。
右肩後方まで大きく引いて放つ日本弓道独特の行射を考えるとき、前記のどの一つが欠けても笄や反転による首折れを起す可能性はありますので、工夫や配慮が必要です。弓力に応じた太さの麻弦を使用すれば、空筈を引いて弓が反転したとしても、弦が瞬間的に切れ、衝撃を吸収する働きをするため首折れに至る可能性は非常に少ないです。
合成弦の場合は、離れの衝撃で笄を起こす可能性が高く、また反転の衝撃では切れないため、その負担が弓にかかり、1回の反転で首折れの破損に至ることも不思議ではありません。
首折れは修理不可能ですから、たとえ1回の反転であっても、損傷は必ず起こっているものと考えるべきで、専門的な点検が必要です。
1000射引いても切れないのが合成弦ですが、この強さを弓士が求める限り、和弓に適した合成弦の開発は不可能と考えます。弦が長持ちする分、弓の負担は大きく消耗も激しいことを理解して下さい。麻弦の場合、200~300射引ければ優秀な弦と言うべきであり、満足すべきであります。合成弦も同じ程度の強度の製品開発が望ましく、弓にも先手の手の内にも優しい和弓用の弦ができることを願っております。
優秀な弓具は使用される弓士の意識の改革から生まれると思います。いつか弓に優しい合成弦が開発された時、理解ある賢明な支持が最も大切ではないかと思っております。優秀な麻弦の供給がままならない現状を考え、合成弦の特性を理解し、弓の負担を軽減するための工夫を凝らし、上手に使っていただくことが最善の策と考えます。
弓の故障・破損を防止するには?
Q4.弓の破損・故障を防ぐために、注意すべき点を教えてください。
弓の破損・故障で代表的なものは、笄(こうがい)と首折れです。このうち笄は概ね修理可能ですが、性能は低下することもあります。首折れに至っては修理不可能でいったん起こしてしまうと、弓師の手でもどうにもなりません。
ただし、こうした破損・故障は日頃の配慮と工夫によって未然に防ぐことができます。常に弦の通り・上下の成りのバランス・張り高を整え、また筈こぼれをしないように中関をしっかりと作る、空筈(矢筈が中関から外れた状態で離れること)をしない、さらに矢束に応じた長さの弓を使用することなどを心がけて下さい。
笄の防止策
強く握り締め、捻り込む行射の場合、上成に無理な負担がかかります。上成が弱くなることで上下のバランスが崩れ、笄を起こし、デキ弓にもなっていきます。
弦跡が真ん中および、やや右に付く方は先手の握りが堅く、笄を起こす可能性の非常に高いといえます。こうした方は、デキ弓になりやすい使い方をしているともいえますので、射技の改善や工夫も必要です。
矢束を長く取る方は、当然長い弓を使用されるわけですが、この場合、弦の種類、矢の重さにも留意する必要があります。
麻弦使用の場合でも、並寸は85センチまで、二寸伸は93センチまで、それ以上の方は、四寸伸以上の弓を使用した方が良く、弓にとって合成弦の使用は麻弦の数倍の負担がありますので、長目の矢、重い矢を使用すべきです(弱い弓の場合で1割前後、強い弓の場合は1割5分程度、麻弦のときより重い矢を使用)。なお矢束85センチ以下でも二寸伸、90センチ位でも四寸伸の弓使用が適している場合があります。
首折れの防止策
首折れの多くは、合成弦使用時の空筈(からはず)から起こるもので、弓力に対して軽過ぎる矢の使用、あるいは弦の通りや低すぎる張り高、極端な緩みや握り締めなどの不用意な行射が原因で弓が反転し、起こります。
合成弦は弓が反転しても切れないため首折れに至るのに対し、麻弦は弓力に適した太さの弦であったら反転の衝撃で切れるため折れることはほとんどなく、空筈の場合でも衝撃を軽減し、反転を防ぐ働きをします。
弦を張ったら弦掛かり、弦の通り、弓把の高さ及び上関板と弦の間隔、中関と筈の調節、上下の成り等の調整をし、弓形を整えてから行射に入るように習慣づけて下さい。また中関をしっかり作るのは当然として、矢筈に丸ヤスリを使って筈溝の奥に膨らみを持たせる加工をしておくと、大きな効果があります(写真17)。

【写真17】矢筈の加工。丸ヤスリを使って筈溝の奥に膨らみを持たせる
弓は弦を外した状態では、弱い力でも簡単に折れるような構造になっています。例えば上関板の一箇所を握って持ち上げたり、また上鉾を突いたり、当てただけで簡単に裂け割れが入ります。これが原因となり行射中、ある日突然、首折れを起こすこともあります。このような事態を防ぐため、弓を持ち歩く時には、長さ約30センチくらいの弓と同じ幅の板状の竹にヒモを付けた用具で、上関板から姫反にかけて保護しておくようにします(写真18)。
また、大変重要な意味があるのに、意外とおろそかにされているのが、弓力と矢の重さの関係です。弓力に対して軽すぎる矢は空筈に近い状態になり、離れの衝撃を受け止めきれず反転につながることがあります。矢押しの良い弓ほど、軽い矢では性能通りの冴えた弦音は出ませんから、重めの矢をお使い下さい。なお、矢の重量については、表(Q2参照)を参考にしていただき、ご自分の射技との相性も考慮にいれながら、最も弦音の冴える組み合わせを見つけて下さい。
首折れは、正常な行射においては絶対に起きないことです。首折れは不名誉な恥ずかしい故障と認識し、未然に防ぐように心がけて下さい。

【写真18】弓と同じ幅の板状の竹にヒモを付けた用具。上関板から姫反を保護する
新弓の取り扱いと育て方
Q3.新弓を購入しました。取り扱いで注意すべき点は?
弓師は、名弓になる素質を持った弓を作ることに最善を尽くします。完成品に育て上げるのは弓士の皆様御自身であり、「使いながら育てる」という意識と気配りをしていただくことが最も大切であります。名弓に育て上げるコツは、頻繁に弓を見、微小な狂いになるべく早く気づき、矯正することです。 特に新弓のうちは一射ごとに弓形を点検することが大切で、何回も見ることで弓の良否を見分ける目が養われます。 以下、新弓を購入された後、やっていただきたいこと、留意していただきたいことを列記します。 *ご購入の際、弦は必ず張ったままお持ち帰りいただき、十分使い込むまで張りっぱなしでお使い下さい。
弓型を紙に写す
新弓を手にされたら、先ず成型を長い紙に写して下さい。上下の成りのバランス、弦の通り、弦の結び目の位置をよく覚えて下さい。上下の弦の結び目の位置は重要で、その弓に合った正しい位置があり、入手された時に印を付けておくと良いでしょう(結び目は、多くの場合中心よりやや左側です)。弦の通りは脳裏に刻んでしっかりと覚え込んで下さい。
合成弦から、麻弦に張り替える
お買い上げの時の弓は、合成弦が張ってあるのが普通です。しばらくはそのままお使いいただき、使い込んで安定したころ、弓力にあった太さの麻弦に替えることをお勧めします。合成弦と違う柔らかい離れの感触と、冴えた弦音、肩味を味わえると思います。 麻弦は、高価で合成弦のように長持ちはしないものの、離れの衝撃を和らげ、弓の負担を軽減する大変意味のある性能を持っております。笄(こうがい)を大幅に減少させ、そして、空筈を引いても反転を防ぎ、万一、反転しても切れて首折れになるのを防ぎます。
張ってすぐ使用しない
弦を張ってすぐ使用しないで下さい。張ったら必ず上下の弦輪が、その弓に合った適切な箇所にあるかを確かめ、弦がかり、弦の高さ、張り顔を調整し、しばらく置き、(捻りが加わらないように)先手の虎口を開いた状態で、矢束八分目くらいの素引きを2~3回行った後、巻き藁および的前に向かいます。目一杯の素引きは百害あって一利なしです。
車内に放置しない
車の中は、夏場は70℃にもなることがあり、接着面の剥離を起こすことになり、弦を張ったまま高温に放置すると、捩れが生じ、弓力が落ちる原因にもなります。また弦を外してある場合は裏反りが深くなり、普通の張り方では胴が抜けることがあります。もし高温下にさらした場合、風通しの良い、涼しい所に置き、胴、握りに負担の掛からないように弦を張り、型調整をした後、十分時間をおいて使用して下さい。
安定期にかけて保管する
弦を張っておく時には、安定器に掛け、特に高温時には弦が左右に動かぬよう紐で結んで置くようにします。安定器は必ず弦を手前にして弓の左側からつけるようにします(右側から掛けたのでは意味がありません)。
弓形を整えてから行射する
名弓に仕上げるには、張り方が最も重要です。弦を掛ける時には、必要以上に押さず、イリキ過ぎる弓を除き、左に倒し、そこから下方に押して弦をかけてください。張ったら必ず本来の正しい形に整えてから、行射されるように心がけて下さい。
その他
細身に仕上げてある弓については、内竹・外竹ともに弓の働き、矢業(やわざ)を考え、相応に仕上げてあります。外竹を替える修理は弓の性能が狂うことになりますので、修理は致しかねる場合もあります。 三か所籐は、五か所巻きの弓に格式において劣ることは決してなく、伝統の正式な巻き方であります。日本弓は全体の調和を考え、黄金比率により上下の配分がなされていることをご勘案下さい。
弓力と矢の重さの組み合わせ
Q2.弓に負担をかけない矢の重さは、どれぐらいが適当でしょう?
下の表は、並寸85センチ、2寸伸90センチ、4寸伸95センチの矢束をとったとき、弓が過度な負担を受けない範囲の組み合わせであります。弓力が10キログラムの時、矢の重さは22グラム(5匁9分)が適当ということになります。
矢の重さは、各自の射技の傾向とも微妙な関連があり、実射で最も弦子の良いときの組み合わせを優先されるのが最良です。
弓力に対して矢が重い分には、弓に対する悪影響はありませんが、軽すぎると故障誘発の大きな原因になりますので、矢飛が悪くならない範囲でなるべく重めの矢をお使いいただくことが、故障を防止することにつながります。また、麻弦の場合、矢の重さで弦の持ちが大きく違います。1~2分重くするだけで実感できるほど長持ちしますし、磨り減った板付けを新しくするだけでも違うものです。
遠的行射の場合は、かなり軽い組み合わせになろうかと思いますので、笄(こうがい:外竹が切れること)、そして反転の危険性も大変高くなることに注意して下さい。
表:一翠弓、吟翠弓における弓力と矢の重さの組み合わせ
| 弓力 | 矢の重さ |
| 10kg | 22g(5匁9分) |
| 11 | 23g(6匁14分) |
| 12 | 24g(6匁4分) |
| 13 | 25g(6匁4分) |
| 14 | 26g(6匁94分) |
| 15 | 27g(7匁2分) |
| 16 | 28g(7匁47分) |
| 17 | 28g(7匁47分) |
| 18 | 30g(8匁) |
| 19 | 31g(8匁27分) |
| 20 | 31g(8匁27分) |
| 21 | 33g(8匁8分) |
| 22 | 33g(8匁8分) |
| 23 | 33g(8匁8分) |
| 24 | 36g(9匁6分) |
「弦の張り方・外し方」と「弓形の調整方法」
Q1.正しい弓の張り方・外し方とは?
弓の育ちの良否は、日頃の弦の張り・外しにあると言っても過言ではありません。弦の張り・外しの巧拙が弓姿(上下の成りのバランス、弦の通り)や弦子(つるね)などの性能にはっきりと現れます。現在多くの方がされている矛先を上方に当てて張る方法は、弓が受ける力の方向や配分に大変無理があり、成りのバランスを崩し、またデキ弓になりがちな力を受けますので、弦を張った後の矯正で強い力を加える必要が生じ、弓力低下を招く原因にもなります。やはり無理な負担のかからない方法で弦を張ることがベストであり基本です。以下に、写真つきで弦の張り方・外し方、また弓形の調整方法を紹介しました。写真と文章でみると、難しく感じられるかもしれませんが、実際にやってみると簡単で、慣れれば一分以内でできるようになります。
弓の育ちは張り方で決まる。このことを念頭に置いて、無理な負担をかけない張り方と、弓形を整えてから使用する習慣を身につけて下さい。
はじめに
和弓の性能を十分に発揮するには、正しい使い方・手入れ方法を知っておくことが大切です。近年、在庫を置いて、枯れた弓を販売する伝統的な販売形態の弓具店が非常に少なくなり、手入れ技術も劣ってきたのが現状です。 当方は枯れた弓を弓具店に出荷することは殆どございませんので、在庫の多いところほど枯れて安定した弓が置いてあるということになります。 こうした状況を踏まえ、「自分の弓は自分で守る・育てる」、つまり弓士の皆様御自身が基本的な手入れ技術を会得することが最善であるとともに必要不可欠であります。 弓具店で枯れた作品を購入されても、少なくても一夏を越すまでは、育てる意識を持つことが必要であり、使い方・手入れ方法に不備があったら決して良い弓には仕上がりません。弓にとって最も過酷な季節の、梅雨から夏場を上手に過ごさせることが良い弓に仕上げる決め手になります。 行射においても弓、矢、弦はお互いに影響し合っており、不備があれば何らかの支障をきたします。なかでも弦は弓に対して大きな影響力を持っていますので、弦の特性を理解したうえで使用していただきたいと思っております。 弓は本来、店頭にあるうちは完成品とは言えず、自ら使いながら序々に完成品に育て上げるものです。 上記のような考えにもとづいて、この項では、弦の張り・外し方から、基本的な手入れ方法、弓と弦の特性など、最良の弓に育てるために弓士が知っておきたい知識をQ&A方式で紹介してあります。重複個所は特に重要なこととご理解いただきまして、ご自身の弓のメンテナンスにお役立て下さい。
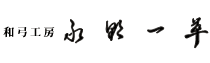



 【写真4】
【写真4】





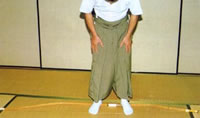



 【写真15】
【写真15】 【写真16】
【写真16】